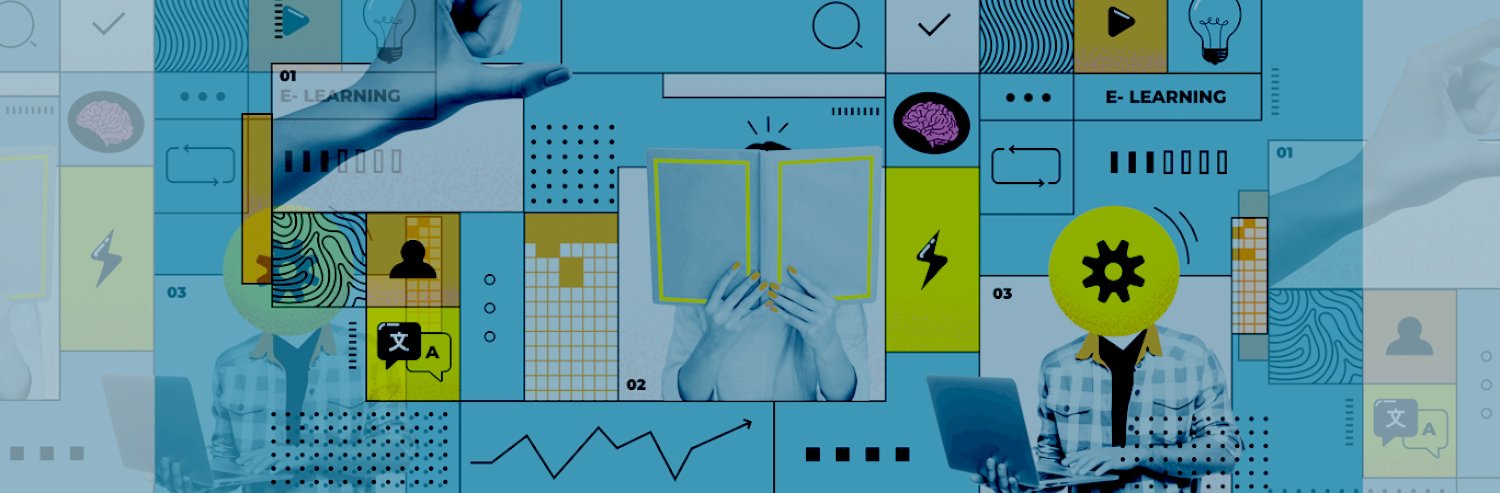機械翻訳はついに「解決」されたのか? アルゴリズム的バベルフィッシュに迫る
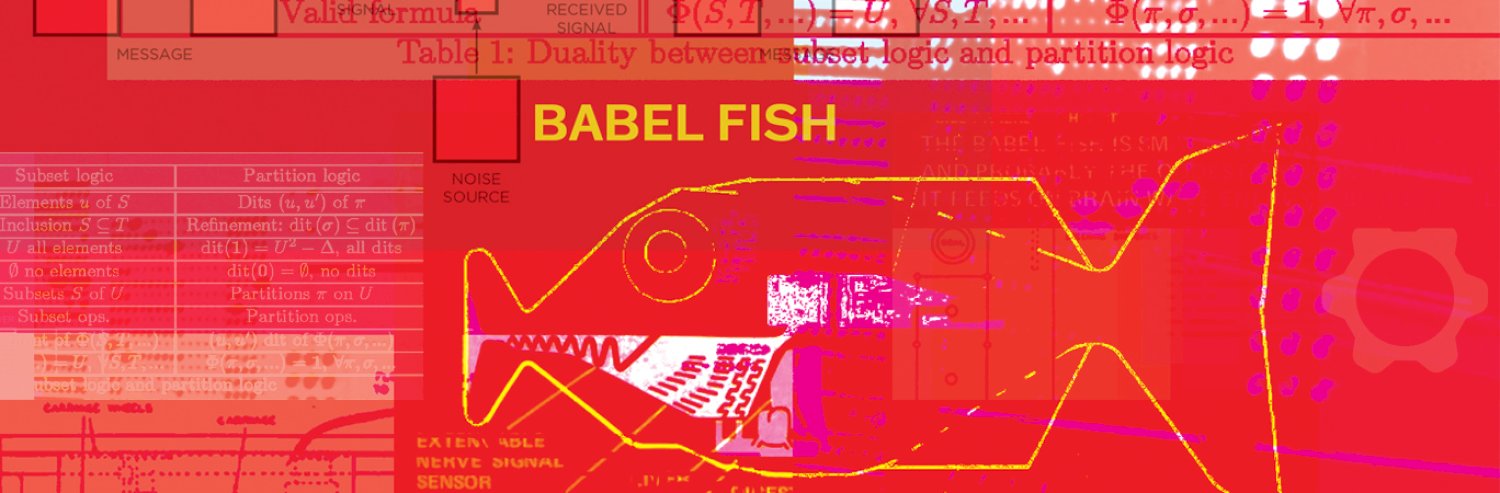
この記事は、AltaVistaのバベルフィッシュから、今日の洗練されたAI搭載ツールまで、機械翻訳(MT)の進化を検証します。進歩により速度と効率性が劇的に向上した一方で、著者は、初期のMTシステムに対するウンベルト・エコの批判を用いて、微妙な文脈、文化的含み、文学的手法の翻訳における持続的な課題を浮き彫りにします。AIは日常的なタスクでは優れていますが、微妙な言語的および文化的差異を処理する上で、人間の翻訳の重要な役割には及びません。この記事は、MTへの過剰な依存を警告し、潜在的な文化の貧困化と人間の翻訳スキルへの価値低下を警告しています。それは慎重なアプローチを提唱し、人間の翻訳者の独自の価値を強調しています。
続きを読む